一般内科
一般内科では、風邪やインフルエンザ、胃腸炎などの急性疾患から、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病まで、幅広い病気の診療を行います。また、原因の分からない発熱や倦怠感、食欲不振、体重減少などの症状についても、丁寧に診察し、適切な検査や治療をご提案します。
日常生活の中で「なんとなく体調が悪い」「疲れやすい」「頭痛やめまいが続く」といった症状にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。内科全般を診る総合的な視点で診察し、必要に応じて専門的な検査や治療を行います。
また、症状や病状に応じて、適切な専門医療機関へのご紹介も可能です。地域のかかりつけ医として、皆さまの健康をトータルにサポートいたします。

主な疾患・症状
- 風邪
- インフルエンザ
- 胃腸炎
- 腹痛
- 嘔吐や下痢
- 尿が近い
- 脱水
風邪
風邪の症状は、くしゃみや寒気、倦怠感から始まることが多く、その後、喉の痛みや頭痛などが現れます。ウイルスによっては、吐き気や下痢などの消化器症状を伴うこともあります。通常、風邪は1週間から10日程度で自然に治りますが、喉や鼻が細菌に二次感染すると長引くことがあります。
インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、突然の高熱、倦怠感、関節痛、筋肉痛などの全身症状が強く現れるのが特徴です。風邪と症状が似ていますが、インフルエンザはより重い症状が出やすく、合併症を引き起こす可能性もあります。
主な症状としては、38℃以上の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感、咳、鼻水、喉の痛みなどが挙げられます。
インフルエンザの潜伏期間は通常1~3日程度で、発症後1週間程度で症状は改善に向かいます。しかし、高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすく、肺炎や脳症などの合併症を引き起こすことがあるため注意が必要です。
胃腸炎
胃腸炎は、ウイルスや細菌などの感染によって胃や腸に炎症が起こる病気です。主な症状としては、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などが挙げられます。ウイルス性のものでは、ノロウイルスやロタウイルスなどが原因として知られています。細菌性のものでは、サルモネラ菌や大腸菌などが原因となることがあります。
症状としては、まず吐き気や嘔吐が起こり、その後、下痢や腹痛が続くことが多いです。発熱や食欲不振、倦怠感などを伴うこともあります。症状が続く場合は、医療機関を受診しましょう。特に、乳幼児や高齢者は重症化しやすいので注意が必要です。
腹痛
腹痛は、みぞおち、上腹部、下腹部、左右の脇腹など、様々な場所に起こりえます。暴飲暴食による腹痛は、比較的心配のないことが多いですが、激しい痛みが生じ、痛みがみぞおちから下腹部に移動する場合は、虫垂炎の可能性も考えられます。
激しい痛みとともに下痢を伴う場合は、便に血液、膿、粘液などが混じっていないかを確認しましょう。腹痛の原因は様々であり、自己判断は危険です。症状が続く場合や悪化する場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
嘔吐や下痢
嘔吐や下痢は、食べ過ぎや飲み過ぎ、風邪などが原因で起こることがありますが、中には他の病気の症状として現れることもあります。安易に吐き気止めや下痢止めを使用すると、病気の診断や治療を遅らせてしまう可能性があります。
原因がはっきりしないのに嘔吐や下痢が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。
尿が近い
排尿回数が多いと感じる場合、それは頻尿かもしれません。一般的には、日中の排尿回数が8回以上、夜間(就寝中)の排尿回数が2回以上の場合に頻尿と診断されますが、排尿回数がそれ以下であっても、ご自身が気になるようでしたら頻尿と言えます。
頻尿の原因は様々で、生活習慣、病気、薬などが考えられます。例えば、過剰な水分摂取やカフェイン・アルコールの摂取、利尿作用のある食品の摂取などは生活習慣に関わる要因です。また、膀胱炎や過活動膀胱、糖尿病、前立腺肥大症などは病気によって頻尿が引き起こされる例です。他にも、利尿薬などの薬が原因となることもあります。
脱水
脱水とは、体内の水分量が不足した状態を指します。健康な成人の場合、体重の約60%が水分で構成されていますが、この割合が低下すると脱水状態となります。
脱水は、体から排出される水分量が増加したり、摂取する水分量が不足したりすることで起こります。
軽度の脱水であれば、喉の渇きや食欲不振といった症状が現れますが、水分を補給することで回復します。しかし、脱力感や眠気、頭痛などが起こるような中程度の脱水状態になると、医療機関で点滴による水分補給が必要となる場合があります。さらに脱水が進むと、意識障害や臓器不全などを引き起こす危険性もあり、緊急の処置が必要となります。
循環器内科
循環器内科では、心臓や血管に関する病気を専門的に診療します。具体的には、高血圧、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全、閉塞性動脈硬化症(PAD)などが対象となります。これらの疾患は、放置すると命に関わる重大な合併症を引き起こすこともあるため、早期発見・早期治療が重要です。
動悸や息切れ、胸の痛み、めまい、手足のしびれ・冷感、むくみなどの症状がある場合は、循環器系の異常が隠れている可能性があります。これらの症状が続く場合は、速やかにご相談ください。診察では、心電図、血圧測定、血液検査などを行い、必要に応じてより詳しい検査を実施します。
また、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病は、循環器疾患の大きなリスク要因となります。当院では、食事や運動習慣の改善指導、禁煙サポートなども含め、生活習慣の見直しを通じて心血管疾患の予防にも力を入れています。
長期的な健康管理をサポートし、患者さんが安心して日常生活を送れるよう、丁寧な診療を心がけています。
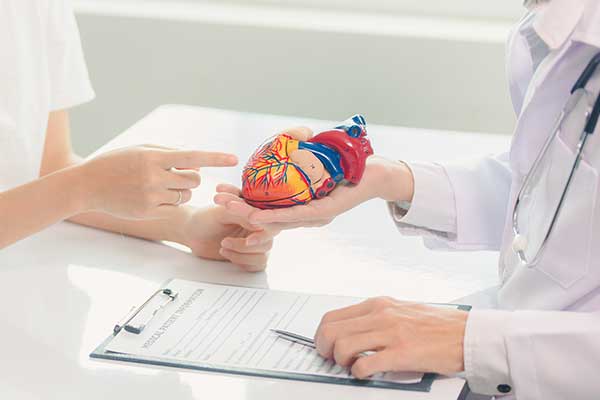
主な疾患・症状
- 動脈硬化
- 狭心症
- 不整脈
- 心不全
- 動脈硬化
- むくみ
- 動悸
- 胸の痛み
動脈硬化
動脈硬化は、血管が硬くなり弾力性を失う状態です。血管内側にコレステロールなどが蓄積し、血管が狭くなることで起こります。加齢とともに進行しますが、生活習慣も影響します。
原因は、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、ストレスなどです。これらが複合的に関与し、動脈硬化を進行させます。
初期には自覚症状はほとんどありません。進行すると、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの合併症を引き起こします。
動脈硬化は様々な合併症を引き起こす可能性があるため、予防が重要です。
狭心症
狭心症は、心臓に血液を送る血管である冠動脈が狭くなることで、心臓の筋肉(心筋)への血液供給が一時的に不足し、胸に痛みや圧迫感などの症状が現れる病気です。
症状としては、胸の痛みや圧迫感が最も一般的です。締め付けるような、押さえつけるような、または焼け付くような痛みが胸の中央や左側に起こります。原因としては、動脈硬化が最も多いです。冠動脈の壁にコレステロールなどが蓄積し、血管が狭くなることで起こります。
狭心症には、労作性狭心症、安静時狭心症、不安定狭心症などがあります。労作性狭心症は、運動時や労作時に症状が現れます。安静時狭心症は、安静時や睡眠中に症状が現れます。不安定狭心症は、症状が頻繁に起こるようになり、心筋梗塞に進行する危険性があります。
狭心症の症状は、個人差があります。症状が現れた場合は、早めにご相談ください。
不整脈
不整脈は、心臓のリズムが乱れる状態です。心臓は電気信号で規則正しく動きますが、この信号に異常があると脈が乱れます。
原因は加齢、ストレス、生活習慣、心臓の病気など様々ですが、不明なものもあります。症状は動悸、息切れ、胸痛、めまい、ふらつき、失神などがありますが、無症状の場合も多いです。
不整脈には、脈が速くなる頻脈性、遅くなる徐脈性、不規則になる期外収縮などがあります。特に、頻脈性不整脈の中には、心室細動や心室頻拍など、突然死につながる危険なものもあります。また、徐脈性不整脈の中には、心臓の働きが著しく低下し、失神や心不全を引き起こすものもあります。
不整脈には危険なものもあるので、気になる症状があれば早めに受診しましょう。
心不全
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態です。様々な原因で心臓の機能が低下し、息切れやむくみなどの症状が現れます。
原因としては、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、弁膜症、心筋症などが挙げられます。これらの病気によって心臓の筋肉が弱ったり、弁がうまく機能しなくなったりすることで、心臓のポンプ機能が低下します。
症状としては、息切れ、むくみ、倦怠感、動悸などが現れます。初期には、運動時や労作時に息切れが起こることが多く、進行すると安静時にも息切れが起こるようになります。また、足や足首のむくみ、体重増加、疲れやすさ、動悸なども見られます。
心不全は、進行すると呼吸困難や肺水腫などを引き起こし、生命に関わることもあります。そのため、早期発見・早期治療が重要です。
むくみ
むくみとは、血液中の水分が血管やリンパ管の外にしみ出し、体内の水分が増えて皮膚の下に溜まった状態を指します。むくみがひどい場合には見た目にも明らかな変化が現れますが、ごく軽い場合には詳しく調べなければ分からないこともあります。
むくみが最も多く現れるのは足と顔の部分です。特に、足首の少し上を指で20~30秒間押さえ、指を離した時にくぼみ(指の跡)が残る場合は、むくみが確認できます。
全身性のむくみは、心臓、腎臓、肝臓などの重大な病気の症状として現れることが多いため、注意が必要です。
動悸
動悸とは、心臓のドキドキとした拍動を普段よりも強く感じたり、速く感じたりする症状のことです。健康な人でも、運動や興奮時などに動悸を感じることがありますが、動悸が頻繁に起こる場合や、動悸とともに胸の痛みや息切れなどの症状が現れる場合は、注意が必要です。
動悸の原因は様々ですが、不整脈、心臓弁膜症、心不全、甲状腺機能亢進症、貧血、ストレス、不安などが考えられます。動悸が続く場合や、動悸とともに他の症状が現れる場合は、早めに医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けることが大切です。
呼吸器内科
呼吸器内科では、咳や痰、息苦しさ、喘鳴(ぜんめい)、胸の痛みなど、呼吸器に関する症状を診察し、適切な治療を行います。気管支炎、肺炎、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、さまざまな呼吸器疾患に対応しています。
長引く咳や息切れ、深呼吸をすると胸が痛むなどの症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。特に、喫煙習慣のある方や、過去に肺の病気を経験された方は、定期的な診察や検査が重要です。当院では、必要に応じて胸部レントゲン検査や呼吸機能検査(スパイロメトリー)を行い、正確な診断を心がけています。
また、アレルギーや環境因子が原因で発症する喘息やアレルギー性気管支炎の治療にも対応しています。適切な吸入薬の使用や生活環境の調整に関するアドバイスを行い、症状のコントロールをサポートします。さらに、COPDの患者さんには、禁煙治療のサポートや、呼吸リハビリテーションのアドバイスも実施しております。
健康な呼吸を維持し、快適な生活を送るために、どんな些細な症状でもお気軽にご相談ください。

主な疾患・症状
- 肺炎
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 呼吸不全
- 息切れ
- ヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音
気管支炎
気管支炎は、気管支が炎症を起こしている状態です。ウイルス感染や細菌感染、刺激性物質の吸入などが原因で起こります。
主な症状は、咳、痰、喉の痛みです。咳は、最初は乾いた咳であることが多いですが、次第に痰を伴うようになります。痰の色は、透明、白色、黄色、緑色など様々です。
気管支炎には、急性気管支炎と慢性気管支炎があります。急性気管支炎は、比較的短期間で治る気管支炎です。慢性気管支炎は、咳、痰が長期間続く気管支炎です。
気管支喘息
気管支喘息は、気道が慢性的に炎症を起こし、様々な刺激に対して過敏に反応する病気です。気道が狭くなることで、呼吸が苦しくなったり、咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)が出たりします。
原因は人によって異なり、ダニやホコリ、ペットの毛などのアレルゲン、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染、タバコの煙や大気汚染、運動、ストレスなどが考えられます。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、タバコの煙や有害物質の吸入などによって、肺の機能が徐々に低下していく病気です。COPDの原因のほとんどは喫煙です。タバコの煙に含まれる有害物質が、肺や気管支を傷つけ、炎症を引き起こします。
COPDの主な症状は、息切れ、咳、痰です。COPDは、進行すると呼吸不全を引き起こし、日常生活に支障をきたすようになります。また、肺炎などの感染症にかかりやすくなることもあります。
呼吸不全
呼吸不全は、肺のガス交換能力が低下し、血液中の酸素が不足、二酸化炭素が過剰になる状態です。原因は肺炎、肺気腫などの肺疾患、心不全、神経・筋肉の病気、外傷など多岐にわたります。症状は息切れが最も多く、他に咳、痰、頻呼吸、チアノーゼ、意識障害などがあります。
急性呼吸不全は早急な治療が必要で、慢性呼吸不全は長期的な管理が必要です。呼吸困難があれば早めに受診しましょう。
アレルギー科
アレルギー科では、花粉症、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹(じんましん)、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、薬剤アレルギーなど、さまざまなアレルギー疾患の診断・治療を行います。
アレルギー症状は、季節の変わり目や生活環境の変化によって悪化することがあり、適切な治療と対策が重要です。当院では、アレルギーの原因を特定するための血液検査や皮膚テストを実施し、患者さま一人ひとりに合った治療方針をご提案します。
治療方法としては、内服薬(抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬)、点鼻薬・点眼薬、吸入薬などの薬物療法のほか、花粉症に対する舌下免疫療法などの根本治療にも対応しております。また、生活環境の改善やアレルゲンの回避方法についてもアドバイスを行い、症状を軽減するためのサポートをいたします。
アレルギーは適切な治療を受けることで、症状を和らげたり、日常生活の質を向上させたりすることが可能です。くしゃみ・鼻水・目のかゆみ・皮膚のかゆみ・呼吸苦などの症状にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

主な疾患・症状
- アトピー性皮膚炎
- 花粉症
- 湿疹
- かゆみ
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が慢性的に良くなったり悪くなったりを繰り返す皮膚の病気です。原因は、遺伝的な要因や環境的な要因など、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
主な症状は、かゆみと湿疹です。湿疹は、顔や首、肘の内側、膝の裏側など、特定の部位にできやすいのが特徴です。アトピー性皮膚炎の症状は、年齢によって変化することがあります。乳児期には、顔や頭に湿疹ができやすく、幼児期には、肘や膝の裏側に湿疹ができやすくなります。
適切な治療を行うことで、症状をコントロールし、日常生活を快適に過ごすことができます。
花粉症
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因で起こるアレルギー疾患です。
主な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどです。これらの症状は、花粉が飛散する時期に現れ、花粉の量が増えるにつれて悪化することがあります。
花粉症の症状は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。集中力の低下や睡眠不足、倦怠感などにより、仕事や勉強に支障をきたすこともあります。
花粉症の原因となる花粉は、植物の種類によって異なります。スギ花粉は、2月から4月頃に多く飛散し、ヒノキ花粉は、3月から5月頃に多く飛散します。
花粉症は、適切な対策を行うことで、症状を軽減することができます。花粉の飛散時期を把握し、マスクやメガネの着用、こまめな手洗い、室内清掃などを行うことが大切です。
湿疹
湿疹は、皮膚に炎症が起こり、赤みやブツブツ、水疱などが現れる状態です。通常、かゆみを伴います。
原因は様々で、外部からの刺激(かぶれ、乾燥、摩擦など)や、体質的な要因(アトピー性皮膚炎など)、細菌や真菌の感染などが考えられます。
湿疹の種類によって症状や特徴が異なりますが、一般的な症状としては、赤み(紅斑)、ブツブツ(丘疹)、水疱、かゆみなどが挙げられます。
湿疹は、放置すると悪化したり、慢性化したりすることがありますので、早めに受診してください。
かゆみ
かゆみの原因物質が特定できれば、それに触れないようにすることで症状を抑えることができます。原因物質を特定することは、かゆみの予防や治療方針を立てる上で非常に重要です。
かゆみを引き起こす物質は多種多様であり、人によって反応する物質も異なります。そのため、かゆみの原因を特定するには、専門医による診断が必要となります。
気になる症状がある場合には、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることをお勧めします。
AGA治療
当院では、AGA(男性型脱毛症)治療を行っております。
薄毛や抜け毛でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
AGAは進行性の脱毛症であり、放置すると徐々に薄毛が進行してしまいます。当院では、患者様一人ひとりの症状や進行度合いに合わせて、最適な治療法をご提案いたします。
「最近、髪の毛が薄くなってきた気がする」「抜け毛が増えた」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

| プロペシアの後発医薬品 | 28日分 6,600円(税込) |
| ザガーロの後発医薬品 | 30日分 5,500円(税込) |
ED治療
当院では、ED(勃起不全)治療を行っております。
EDは、ご本人にとって大変デリケートな問題であり、なかなか相談しづらいと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、EDを放置してしまうと、ご自身のメンタル面にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
当院では、患者様一人ひとりの状況に合わせて、丁寧なカウンセリングを心がけております。安心してご相談いただけるよう、プライバシーにも配慮した環境を整えております。「もしかしてEDかも?」と感じたら、まずはご相談ください。早めのケアが、心身の健康を取り戻す第一歩となります。

| バイアグラのジェネリック(シルデナフィル) | 1錠 1,100円(税込) |
| レビトラ | 1錠 2,000円(税込) |
| レビトラのジェネリック(バルディナフィル) | 1錠 1,600円(税込) |
| シアリス | 1錠 2,200円(税込) |
| シアリスのジェネリック(タダラフィル) | 1錠 1,700円(税込) |
